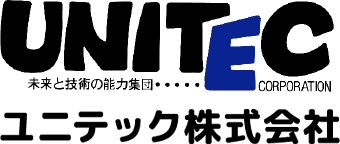近年、環境問題への関心が高まるなかで「カーボンニュートラル」という言葉を耳にする機会が増えてきました。カーボンニュートラルとは、排出される二酸化炭素(CO₂)の量と、吸収または削減されるCO₂の量を差し引きゼロにすることを意味します。

従来からよく使われている「省エネ」や「エコ」という言葉は、「電気の節約」や「CO₂の削減」を意味していました。ただし、それらはあくまで減らすことが前提であり、「ゼロにする」という発想までには至っていませんでした。
カーボンニュートラルはそこから一歩進み、「削減するだけでなく、吸収する」という考え方を取り入れることで、最終的に排出量をゼロに近づけるという点がポイントです。工場や発電所、自動車などから排出されるCO₂を、再生可能エネルギーの利用や省エネ技術、森林保護などによる吸収量で差し引きゼロにするといったイメージです。CO₂を全く出さないのは現実的ではないので、「出した分をきちんと相殺し、地球全体として増えない状態を維持する」ことを目指す形です。この概念は、日本国内だけでなく世界中で、産業界が共通して取り組むべきテーマとして注目を集めています。
Contents
モータ製造メーカーがカーボンニュートラルを推進する意義
我々にとっても、カーボンニュートラルは避けて通れないテーマです。日々の開発業務の中でも、意識すべきポイントになっています。その理由は大きく分けて2つあります。
1つ目は、「モータは産業全体の脱炭素化に大きく貢献できる」という点です。おもちゃや家電といった身近なものから、工場設備や自動車に至るまで、モータはあらゆる場面で使われています。現代社会においては欠かせない存在と言っても過言ではありません。そのモータを省エネ設計にしたり、製造時のCO₂排出を減らしたりすることは、社会全体のCO₂削減につながるのは容易に想像できると思います。
2つ目は、「企業の信頼性や存続意義を高めることにつながる」という点です。カーボンニュートラルを推進している企業は、取引先やエンドユーザーから信頼を得やすくなります。さらに、各種規格類には、省エネや環境対応に関するルールが設定されている場合もあり、こうした取り組みを怠れば、最悪の場合は製品が販売できない、購入してもらえないといった事態もあり得ます。つまり、カーボンニュートラルへの対応は、もはや必須条件となりつつあるといえます。
自社内で取り組めること

省エネ設備の導入
最も取り組みやすいのは、省エネ設備の導入です。工場やオフィスは長時間稼働するため、設備更新時に省エネ型を選択することが非常に重要になります。ユニテック静岡事業所では、すでに全ての照明をLED化し、照明における年間電力消費を約30%削減することに成功しました。
古い設備を使い続けることは、CO₂排出量が増加するだけでなく、突発停止や修繕費用の増大といったリスクを抱えることにもつながります。そのため、省エネ設備の導入は安定稼働を守るための観点からも優先度が高いのです。
研究用や試作用、品質評価用、さらには量産設備など、事業所には大小さまざまな設備があります。これらを一度にすべて入れ替えるのは、まだ使える設備を廃棄してしまうことになり現実的ではありません。
しかし、新たに設備を導入する際に「消費電力が小さい機器を選ぶ」「複数の機能を兼ね備えた設備を採用する」といった工夫を積み重ねることで、省エネ効果は確実に高まります。稼働率の高い設備だからこそ、省エネ化の効果は非常に大きく、CO₂削減に直結する取り組みといえるのです。
再生可能エネルギーの導入
エネルギー供給の面でも、静岡事業所は積極的に取り組んでいます。当事業所はEnneGreen®の証明書を取得し、実質的に100%再生可能エネルギー電力を利用しています。これはCO₂排出削減に大きく貢献するものであり、社会的にも意義のある施策です。ただし、再エネの利用には安定供給性やコスト変動の課題もあります。そのため、将来的には自家発電設備や蓄電システムとの組み合わせを検討し、持続的に利用できる体制を整えていく考えです。
国際規格の理解
JIS、ISO、IEC、EN、CCC等の国際的な規格は、ものづくりを行う上で避けて通れないルールです。これらは製品を開発・販売するうえでの「世界共通言語」ともいえます。近年はこうした規格の中に、省エネ性能や環境配慮に関する基準が盛り込まれることも増えてきました。つまり、国際規格の理解は「世界基準の省エネ設計」を目指すことでもあります。最新情報を常にキャッチし、開発する製品の性能ターゲットを世界基準に合わせていくことが、モータメーカーにとって非常に重要です。
設計段階でのシミュレーション活用
近年ますます重要になっているのが設計段階でのシミュレーション技術の活用であり、試作を行ってから問題点に気付くのではなく、事前に解析を実施することで効率の良い形状や発熱・損失の少ない回路設計を検討でき、これによって無駄な試作や再設計を削減し、開発工数の効率化のみならず資源やエネルギーの節約にもつながります。高性能PCや解析ソフトの進化により比較的容易に導入が可能となってきたとはいえ、試作機製作を完全にゼロにするのはリスクが高く、段階的に活用を進めていくことが望まれます。
当社では過去70年分のバックデータを活用し最適設計を行うことで試作回数を抑制してきましたが、解析ソフトの導入には人材育成やデータ整備といった課題が残されています。他社の失敗事例からも分かるように重要なのは技術そのものよりも「どう使いこなすか」であり、実際にはシミュレーションと現物評価が一致しないことも多く、解析結果に依存しすぎたことで大きな問題を招いた事例も確認されています。
一方で、適切に活用することで大きな成果を挙げている企業も存在しており、新技術は一見万能に見えるものの決して魔法ではなく、あくまで使いこなし方次第で真価を発揮するものであるという点を忘れてはなりません。当社としてもこの点に留意しながら、今後シミュレーション技術の導入に向け、着実に実務へ落とし込み、効率化と社会的意義の両立を図っていきたいと考えています。
植林活動
ユニテック静岡事業所においては、自社内だけで大規模に森林整備を行うのは難しい面がありますが、それでも「自然のCO₂吸収装置」としての緑を増やしていくことは、カーボンニュートラルの実現に直結するだけでなく、地域環境の保全や生態系の維持にもつながる意義ある取り組みです。
そこで、まずは工場敷地内の緑化や植栽の充実を進めるとともに、自治体や外部団体との協定や共同事業を通じて森林育成活動に参画し、長期的にCO₂吸収効果を高めていくことを検討しています。こうした取り組みはCSR(企業の社会的責任)の一環として社外からも高く評価されるものであり、安定した事業活動と地域社会への貢献を両立させるうえで重要なポイントであると考えています。
お客様への製品提供の中で間接的に取り組めること

モータ消費電力の省エネ化
我々が最も取り組むべきことはやはり、モータの消費電力をいかに抑えるかという点です。一ワットでも下げることができれば、社会全体に与える影響は大きいです。当社は長年のモータ開発を通じて、トルク・回転数・効率のバランスを最適化する知見を培ってきました。これをもとに「同じ仕事量をより少ない電力で実現する」設計を目指しております。
モータの省エネ化は、お客様の製品の省エネ化に直結するので、お客様にも喜ばれる大変有意義な取り組みといえます。このあたりに関しては、別記事でも取り扱っております。参考にしていただけますと幸いです。
リユース・リサイクルの積極推進
モノづくりの現場ではどうしてもプラスチック成形部品や成形マグネット、アルミダイキャストで生じるランナーのように廃材となる部品や材料が発生しますが、これらを積極的にリユース・リサイクルすることは、新たな資源を採掘・精錬する際に生じる環境負荷を低減する効果があり、特に製造に多くのエネルギーを要する磁石などを再利用できれば、省エネルギーと省資源の両面から非常に効果的です。
ただし再利用には注意が必要であり、メーカーの指定や各種規格に基づいて行うことが前提となります。たとえばプラスチック材を再び溶かして新しい部品を成形する際には、強度を確保するために「再利用材をどの割合で混ぜられるか」が定められている場合があります。環境配慮を優先するあまり、製品性能が低下してしまっては本末転倒です。
ユニテックではルールの範囲内で適切なリユース・リサイクルを行い、環境と品質を両立させています。
ランナーとは
プラスチック成形やアルミダイキャストで部品を作るときに、材料(溶けた樹脂や金属)を金型に流し込むための通り道を「ランナー」と呼びます。プラモデルを組み立てる際、部品を一つ一つフレームから取り外す作業を行ったことがある方もいらっしゃるかと思いますが、そのフレーム部分がまさに「ランナー」です。部品そのものではなく、材料を流す通路が固まったものです。ご自宅でも廃棄するものかと思いますが、ものづくりの現場でも同様に不要物となり、廃材として処理が必要になります。
製造ラインの最適化・共用化
多品種少量生産の中でも、複数製品を共用ラインで製造する工夫を進めています。これにより設備台数を抑制し、省エネと生産効率を両立させています。ただし、受注変動への柔軟対応も求められるため、バランスの取れた運営が課題です。
部品共通化
新製品を開発するたびに、部品の形状や寸法、材料を新しく設計していては、似たような機能を持つ部品が製品ごとに増えていってしまいます。そうなると、製造現場では金型の数が増え、製品ごとに金型を交換する工程=段取りも必要になります。さらに組立工程でも専用の設備が増えるなど、対応すべきことがどんどん増えてしまいます。
たとえば「ネジの種類を全製品で一つに統一する」「プラスチック材をABS樹脂に統一する」といった工夫ができれば、モノづくりの手間を減らせるだけでなく、部品管理もシンプルになり、生産コストの削減にもつながります。一つでも多くの部品を複数の製品で共用できるように、設計段階から工夫することが大切です。部品の共通化は生産効率を高めると同時に、廃棄部品の削減にもつながり、環境負荷を低減できる効果的な取り組みです。
カーボンニュートラルの取り組みも積極的に行うユニテックに今後もご期待ください
ユニテックでは、安全・品質・環境の三本柱を軸に、従業員一人ひとりが日々の改善活動を積み重ねています。現場の実践を通じて、カーボンニュートラルへの取り組みを確実に前進させ、社会に貢献できる運営を続けてまいります。