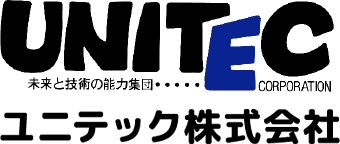世の中のあらゆる電子機器の利便性を高める役割として、バッテリーは非常に重要な装置となってきています。私たちの生活でその恩恵を受けていることがわかる言葉として、「ワイヤレス(コードレス)」という言葉があります。具体例としては、ワイヤレスイヤホン、コードレス掃除機、ワイヤレスマイク、コードレス電話機などなど。これらは、機器自体に電気を蓄える機能=バッテリーをもたせることで、電力を供給する電線をなくす=ワイヤレスを実現している機器達です。
現代においては、バッテリーはあまりにも生活に浸透しており、その存在を感じることがないほどですが、この「ワイヤレス」という言葉を意識すると、バッテリーのあらゆる箇所への存在を感じることができます。
さらに近年、あらゆる機器が小型化・高性能化していく中で、バッテリーの重要性は年々高まっています。特に、ドローンやホビー用途、スマートフォンやノートPCなど、「軽くて、薄くて、パワーがほしい」領域では、リポバッテリー(リチウムポリマー電池)とリチウムイオンバッテリーという2種類が広く使われています。
我々の生活に不可欠なこの2種類のバッテリーについて、今回は深掘りして行こうと思います。

Contents
リポバッテリーとリチウムイオンバッテリー
大前提としてバッテリーは主に下記の3つの要素から成り立っています。
①プラス電極
②マイナス電極
③電解質
電極にどのような材料を使うか、電解質に何を使うかが、バッテリーの性能を決めることになります。今回取り上げるリポバッテリー・リチウムイオンバッテリーは、ともに、リチウムイオンが正極と負極の間を行き来する、という点においては同じ原理 を持っています。
では何が違うかというと、③の電解質が大きなポイントとなります。
リポバッテリーとは
リポバッテリーは「リチウムポリマーバッテリー(Lithium Polymer Battery)」の略称であり、③の電解質に「高分子ポリマー材料」を採用しています。ポリマー状(=半固体)の電解質を使用していることでさまざまな恩恵が得られます。
リポバッテリーの基本構造
正極(リチウム金属酸化物)
コバルト酸リチウムなどのリチウム金属酸化物が使われます。
負極(黒鉛)
リチウムイオンを吸蔵・放出する機能を持ちます。
セパレータ
電極同士が接触しショートしないように隔てる絶縁材の役割をする薄膜。小さな穴が空いており、リチウムイオンだけが通り抜けることができます。
電解質(ポリマー)
電極間をつなぐ存在。リチウムイオンが溶け込んでおり、リチウムイオンが移動するための通り道として機能します。半固体のポリマーが使われます
外装(ラミネートフィルム)
乾電池のような金属缶ではなく、軽量なアルミラミネートフィルムで密封されることが多いです。これにより、薄型化・軽量化・自由形状の実現に大きく寄与しています。
リチウムイオンバッテリーとは
リチウムイオンバッテリーは電解質に「有機物の電解液」を採用しています。すなわち電解質は液体を使用しており、これによりリポバッテリーの特徴との差が生まれます。
リチウムイオンバッテリーの基本構造
正極(リチウム金属酸化物)
コバルト酸リチウムなどのリチウム金属酸化物が使われます。
負極(黒鉛)
リチウムイオンを吸蔵・放出する機能を持ちます。
セパレータ
電極同士が接触しショートしないように隔てる絶縁材の役割をする薄膜。小さな穴が空いており、リチウムイオンだけが通り抜けることができる。
電解質(液体)
電極間をつなぐ存在。リチウムイオンが溶け込んでおり、リチウムイオンが移動するための通り道として機能します。有機物の電解液が使われます。
外装(金属ケース)
金属で構成された円筒形、角形などが多く、堅牢な構造。
リポバッテリーとリチウムイオンバッテリーの違い
ここまで説明した通り、両者はどちらも同じリチウムイオン反応を利用した二次電池ですが、構造が異なることで特徴の差が生じます。細かく詳細を説明していきます。

性能や特性面での違い
エネルギー密度
どちらのバッテリーも、エネルギー発生に寄与する材料は同じ性能であるため、両バッテリーのエネルギー密度は同じといえます。ただ、その製造プロセスの違いにより、一般的にはリチウムイオンバッテリーの方がエネルギー密度は高くできます。リチウムイオンバッテリーは、頑丈な金属ケースに内容物を隙間なく封入する構造が一般的です。ケースが頑丈であるため、圧力をかけて封入が可能であり、この構造によって体積あたりのエネルギー物質を多くすることができ、エネルギー密度を高くできます。
一方リポバッテリーは、積層された電極をラミネートパウチで封止する構造のため、内部の圧縮力はさほど高くできません。この差がエネルギー密度に現れます。
放電性能(Cレート)
リポバッテリーはリチウムイオンバッテリーに対し、内部抵抗を低く抑えられる構造となっています。内部抵抗が低い方が放電時に発生する熱を下げることができ、瞬間的な電力供給には有利となります。そのため、リポバッテリーの方が放電性能は高いといえます。(Cレート数値が高い)
形状自由度
リポバッテリーはパウチ構造のため、薄型、曲面など、変則形状に対応でき自由度が高いバッテリーです。筐体設計に合わせたセル設計も比較的容易に行えます。一方リチウムイオンバッテリーは、サイズで規格化されており、基本的に形状選択肢は限られます。もちろん構造上、筐体に合わせた設計も可能ですが、規格外の対応となるため費用が大きく変わることになるかと思います。
重量
リポバッテリーは外装がフィルムであり、小型・軽量。リチウムイオンバッテリーは金属ケースを採用しているため、同じ容量ではやや重くなる傾向にあります。
安全性
どちらのバッテリーが安全であるかという話は、前提条件をどのように設定するかで変わってくるので、理解には注意が必要だと筆者は感じています。単純に、両バッテリーを「単体」で比べたとき、下記の理由でリポバッテリーの方が安全性は高いといわれます。
・電解質が燃えにくい(リチウムイオン電池の電解液は引火点 40度程度と非常に低いため、相対的にリポバッテリーの方が燃えにくい)
・有害物質がリチウムイオン電池と比べて少ない
・液漏れのリスクが低い(電解質が半固体であるため、漏れたとしても流れにくい)
・仮にショートしても、ガスが発生するだけで済むことが多い
一方で、工業製品として完成されたバッテリーとして考えたときは、リチウムイオンバッテリーの方が安全といわれます。バッテリーとしての機能だけでなく、金属ケース部分に安全装置が付加されていることが多いためです。具体的には、下記のような機能です。
・PTC:過熱時に電流を制限し、熱暴走を防ぐ機能
・CID:内部圧力が上昇した時に、機械的に電流経路を遮断する機構
・ガスベント:圧力が高まると開放されるガス抜き弁
リポバッテリーは現物に触れてみれば一目瞭然なのですが、表面が柔らかく、衝撃や曲げに弱く、保護機構も制限されるため、取り扱いによる安全性リスクは相対的に高くなる傾向があります。
コスト
どちらのバッテリーも世界的に大量生産されており、製造ラインも成熟しています。しかし、規格サイズが決まっているリチウムイオンバッテリーの方が、やはりコストメリットが大きく、同容量なら基本的にリチウムイオンバッテリーの方が安価といえます。リポバッテリーは特殊用途向けも多く、生産ラインも汎用性が低いため、コストが高くなりやすい傾向があります。
用途面での違い
リポバッテリーが得意な用途
ケースがラミネートであること、内部抵抗が低いことから、軽量・高出力・瞬間的な電力供給が求められる用途に向いているといえます。具体的には、ドローンやラジコンなど、限られた空間に柔軟に配置が必要で、急加速・急発進が必要な場面に活躍しています。リポは「高放電性能 × 軽量」という唯一無二の特性を持つため、こうした用途に強く合致します。
リチウムイオンバッテリーが得意な用途
液体電解質は、ポリマー電解質よりもイオン伝導度が高いこと(温度変化に強い)などから、リチウムイオンバッテリーは安全性の他に、寿命・電圧安定供給の観点でも、リチウムポリマーバッテリーより優位となります。そしてリポバッテリー・リチウムイオンバッテリー共通の特徴であるエネルギー密度が高いという特徴から、大容量が必要な用途、長く使うことを想定した機器や、バッテリー交換を想定していない(もしくは長期で交換する)機器に使用されます。具体的には、スマートフォン、ノートPC、電気自動車(EV)などにも使われています。
安全性と取り扱い方法の違い
リポバッテリー
外装はラミネートであり、外部衝撃や物理的変形に弱いため、単純な持ち歩きでも丁寧な扱いが必要です。専用充電器を使用することはもちろんのこと、過充電・過放電を避け、高温・水濡れ・強い衝撃・金属製品との接触にも注意が必要といえるため、専用ケースに入れて保管することが大切です。
リチウムイオンバッテリー
ケースと内部保護機構のおかげで、衝撃耐性・ガス圧管理・過電流対策がセル単体で成立しているものが多く、ユーザにも扱いやすい構造です。とはいえ、高温高湿を避ける、直射日光を避けるなど、工業製品に一般的にいえる注意は守ることが大切です。
また、両方のバッテリーにいえることですが、バッテリーの寿命を延ばすためには、常に100%充電しない方が良い場合が多いです。電池残量が20%程度になったら充電を開始し、80%前後で充電を終えるのが理想的です。最近は、リチウムイオンバッテリーの機能として、最適な充電がなされるよう、制御回路が搭載されているものも出てきています。
まとめ
両者の優劣は一概に決められるものではなく、あくまでも「用途に応じた最適解」が異なるという関係です。
リポバッテリー
→ 軽量・高出力・短時間でパワーが必要な用途向け
(ドローン、ラジコンなど)
リチウムイオンバッテリー
→ 長時間稼働・安全性・安定供給が最重要の用途向け
(スマホ、PC、工具、家電、EVなど)
構造の違いが性能に直結するため「なぜそのバッテリーが使われるのか」を理解しておくと、設計の自由度も広がります。
ロボットやAGVなどの大型デバイス用のリチウムイオンバッテリー
ユニテックでは、自社でリチウムイオンバッテリーも扱っております。DCモータの動力源としてはもちろん、バッテリー単体でのご相談も大歓迎です。ぜひ一度ご相談ください。