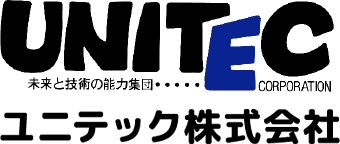電気自動車を筆頭に、近年新しい形の移動手段が増えてきていることは、みなさんも感じていることと思います。電動アシスト付き自転車や電動キックボード、ハンドル型電動車イスなどのパーソナルモビリティと呼ばれる業界や、配膳ロボット、AGV・AMR(自動搬送ロボット)など、ロボット業界にて注目を浴びているのが、このインホイールモータです。
インホイールモータとは、その名の通り「ホイールの中に組み込まれるモータ」です。回転する車輪の内部に組み込まれるモータで、モータの回転軸をダイレクトに車輪に接続、駆動輪として機能します。
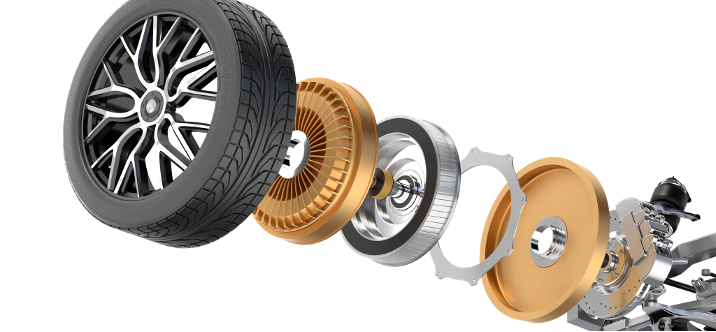
新しい技術のように思われますがそんなことはなく、かつては実用化されていました。あまり知られていませんが、1800年代末から1900年代始めには電気自動車が主流の時代があり、その際実際に使われていた技術です。その後、エンジン技術が発達したことで、電気自動車と共に長らく市場から姿を消していました。電気自動車の需要が高まってきた今、新たに注目されているモータです。
Contents
インホイールモータの構造・仕組み
通常、モータによって駆動輪を回転させる際は、1台のモータの回転軸をシャフト、ギア、チェーンなどを介して、各駆動輪に動力を伝達する形をとります。(エンジン車のエンジンをモータに置き換えるようなイメージ)
この場合モータは1台で済みますが、駆動輪に動力を伝達するまでにさまざまな機構が必要となるため、構造は複雑になり、エネルギー伝達にもロスが発生するという課題があります。
一方インホイールモータは、駆動輪付近にモータを配置し、車輪を直接駆動します。
モータの数は増えますが(駆動輪の数だけ必要になる)、中間の伝達機構がなくなった分エネルギーのロスがへり、自動車であればアクセル操作に対するレスポンスが良くなることが期待できます。
また、左右の車輪が別々のモータで駆動するため、独立して制御が可能となり、ハンドル操作の自由度を向上させることが可能です。

例えば、自動車の横移動。従来型の1台のモータで全ての駆動力をまかなう自動車の場合、ドライブシャフトと呼ばれる左右の車輪をつなぐシャフトが必須となります。この影響で、ハンドルを限界まで回しても車輪を真横に向けることは構造的に不可能でした。
しかし、インホイールモータを使うと車輪の回転方向の自由度が上がり、車輪を真横にまで回転させることが可能になります。すると、自動車を真横に動かすことができるため、縦列駐車などが非常に楽になります。インホイールモータの未来的な可能性を感じられるポイントです。
ベースとなるモータは、高効率・高耐久のブラシレスDCモータが主流となりつつあります。ギア機構、ブレーキ機構、センサ類(エンコーダやホールセンサなど)などさまざまな要素を内蔵し、モータ単体としては非常に多機能なものです。
インホイールモータの利点
駆動系の簡素化、高効率な動力伝達
先程もお伝えした通り、機械エネルギーを伝達する機構(シャフト、ギア、チェーンなど)を省略可能です。動力を直接車輪に伝えるため、ロスが少なく、高いエネルギー効率が実現できます。エネルギーロス低減により、バッテリーの長持ちにもつながります。
また、機構省略により空いたスペースを別の用途に使用可能。車体の小型化や、バッテリー体積の増加、自動車であれば車内空間を広げるなどといったことも可能です。
個別制御が可能
各車輪を独立して制御することが可能です。従来は左右の車輪をドライブシャフトでつなげていたため、左右の車輪は必然的に同じ回転数となることが基本でした。インホイールモータは、それぞれの車輪は他の車輪と物理的につながっていないため、個別に回転数を変更することが可能です。
これにより、カーブを曲がる際の左右の写真の回転数差は無視できますし、滑りやすい路面でも適切な回転数の調整を行うことで、安定した走行が可能になります。
車体の向きを変えずに移動方向の変更が可能
前項でも少し触れましたが、インホイールモータを使うと、車輪を機械的に独立させることができます。イスや台車などについている「キャスター」をイメージしてみてください。それぞれが360度、くるくる回りますよね。
インホイールモータを使うと、車の車輪を、キャスターのようにくるくる回転させることが可能になります。これにより、車体の向きを変えずとも、斜め方向、真横方向に移動することができたり、その場で回転して向きを変えたりすることも可能になります。
弊社では、このキャスターのようなステアリング機構を搭載したインホイールモータを取り扱っております。ご興味ある方は「車輪付きモータ(AGV・AMR向け)」をご参照ください。
回生ブレーキとの相性が良い
ハイブリッド自動車などで聞いたことがある方も多いと思いますが、モータは減速時に発電機として機能させることができます(これを回生ブレーキと呼びます)。途中に伝達機構を挟まず、モータが直接車輪に接続されていることで、回生ブレーキによるエネルギー伝達のロスが少なくなるため、発電効率が高くなることにつながります。回収効率が高く、省エネ性にも寄与します。
インホイールモータの欠点
バネ下重量の増加
モータをホイール内部に配置することで、「サスペンションより下」を意味する「バネ下」と呼ばれる部分の重量が増加します。このバネ下重量は、特に人が乗る乗り物では重要視されるパラメータです。この重量が大きいほど、走行時の乗り心地や操縦安定性に悪影響を与えやすくなります。
インホイールモータは、必然的に車輪の重量が従来よりも大きくなり、サスペンションよりも下に配置されるものなので、避けようがないデメリットポイントといえます。
冷却性能の課題
ホイール内は空間が限られており、熱がこもりやすいため、長時間・高負荷の使用で発熱による性能低下が懸念されます。限られた空間で大きな出力を発揮するためには、冷却対策は必須です。電気自動車用インホイールモータ開発では、油冷技術の採用が研究されています。
衝撃や水・塵への耐性が必要
当然ながら、車輪は外部環境にさらされています。インホイールモータはそのような場所に配置されるため、防水・防塵・耐衝撃性をクリアできるような設計が必要となります。
コスト
駆動する車輪それぞれにモータを用意しなければいけないため、多くの場合モータの数が増えます。また、その名の通りホイールの中の限られたスペースにモータユニットを収められたモータですので、開発、製造、部品のコストが高く、モータとしてのコストは高くなる傾向にあります。
実用化のための課題
インホイールモータは電気自動車において期待されており、話が挙がることが多いのですが、筆者が調べた限り、まだ正式採用されたことはないようです。
モータショーなどで、インホイールモータが搭載されたコンセプトカーがお披露目されたことはありますが、実用化するにはまだ課題が多いようです。先に挙げた欠点面の解決策などの研究を各社進めている様子ですし、バイクではすでにインホイールモータ搭載モデルが多数存在しますので、電気自動車への実用化もそう遠くないかもしれません。
インホイールモータの用途

EV(電気自動車)
先述したように、インホイールモータ搭載された製品はまだ存在しない様子です。調べると、日立製作所では電気自動車用のインホイールモータを開発したという情報も出てきます。実用化にむけた研究が日々進められている様子です。今後の軽量化技術や冷却性能の進化が期待されます。
バイク(二輪車)
電気自動車に先駆け、電動バイクや電動スクーターにおいては、すでにインホイールモータが採用されています。電動バイクでは当然ながらバッテリの搭載が必須です。しかし、バイクはそのサイズから搭載スペースに制約があるため、モータをホイールと一体化できるインホイールモータは電動バイクにとって好都合なものでした。
モータをホイール内に収めることで、スペースの削減が図れ、車体部分をバッテリーや制御機器の搭載に使えるため、車体設計を有利に進められます。こういった利点から、普及が進んでいます。
AGV・AMR
近年のネット通販の拡大や人員削減などを目的とし、物流倉庫や製造現場ではAGV(無人搬送車)、AMR(自律移動ロボット)と呼ばれる荷物を運ぶロボットが活躍しています。
無駄のない細やかな動きができれば、作業効率も上がるため、高い旋回性が求められます。各車輪の制御を独立して行えるインホイールモータはうってつけといえます。弊社でも、AGV・AMR向けのモータを販売しております。
インホイールモータをお求めならユニテックへお任せください
ユニテックは、お客様の利用用途に合わせた最適なモータを設計・製造いたします。インホイールモータ開発・製造ならユニテックへぜひご相談ください。