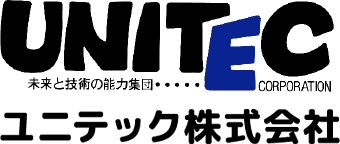病院ではさまざまな医療機器が活躍していますが、医療機器にモータが使われているとイメージできる人は少ないかもしれません。筆者自身も、モータ開発の仕事に携わるまでは同じ認識でした。筆者は実際に、医療機器の開発に参加したことがあり、そこに搭載するモータモジュールを設計した経験があります。
そういった背景もあり、医療機界ではモータは必須装置であることは理解しています。では、なぜ医療機器とモータの関係が一般に知られていないのか。これはまさに、「医療機器に使われるモータに求められること」が関係していると筆者は感じています。今回は、医療機器に使われるモータに求められる主要な要件について解説し、さらに具体的な使用例についても見ていきたいと思います。

Contents
医療機器に使われるモータに求められること
長寿命・メンテナンスフリー
医療機器には、24時間体制で稼働するものや、使用中に故障してしまうと命に関わるような装置も少なくありません。そのため、モータの寿命が短かったり、定期的なグリスアップやブラシ交換が必要であったりした場合、事故が起きないよう頻繁なメンテナンスが必要となります。しかしメンテナンスとなると、そのたびに機器を停止しなければならず、治療現場では大きな支障となります。そのため、長寿命で、かつメンテナンスをほとんど必要としない構造が求められます。
具体的には、ブラシレスDCモータの採用や、高品質ベアリングによる寿命延長が一般的です。また、微小な動作・制御の繰り返しが行われる装置の場合は、摩耗や経年変化によるガタつきを極力抑える高精度な設計が求められます。
高トルク・高出力密度
医療機器は、内部に電子基板、センサー、冷却構造などに加え、機器によっては、薬液配置スペース、薬液を流すためのチューブなど、多数のパーツを持つため、モータに割けるスペースは非常に小さいのが現実です。そのため、小型でも十分なトルクを発生できる設計(高出力密度化)が求められます。また、医療機器では、「滑らかな・一定の力」で動作することが非常に重要です。
例えば、輸液ポンプは薬剤を正確な量で押し出す必要があり、このときトルクの不足やばらつきがあると、薬液の送り出しが途切れたり、微細な誤差が生じたり、医療行為の精度が悪化することに直結します。そのため、高トルクを安定して出力できるモータ(トルクリップルが少ない設計)が求められます。
高トルク化のためには、磁石材料にネオジム磁石などの高性能磁石を使用したり、コイルの巻線密度を高めたりするなどの工夫が行われます。また、制御回路と組み合わせることで、効率的にトルクを引き出す設計が採用されています。
高効率・低発熱
医療機器の内部は、精密な電子回路やセンサが多数組み込まれているため、モータの発熱は機器全体の精度や安全性に影響を及ぼします。さらに、患者の体内へ送り込まれる薬液や血液に近接して使用されることも多く、モータの温度上昇がこれらに影響を与えると、大きな事故に結びつかないとも限りません。こういったことから、医療用モータでは高効率・低発熱設計が求められます。
損失を減らすための巻線密度最適化や、モータコアの材質・形状の最適化、適切な放熱設計などといったことが重要となります。また、制御回路面でも効率を重視した設計を採用し、必要なトルクを発生させつつ無駄な電流を抑える制御技術で省エネ・低発熱化を実現する工夫がされています。
患者への心理的負担を軽減するための要素
お待たせしました、この要素が、冒頭申し上げた話につながってきます。医療機器用モータに求められる特徴として、他の業界とは少し異なる視点があります。それが、「患者への心理的負担を軽減する」という視点です。
具体的には、「柔らかなデザイン」・「静音性」・「低振動」の3要素です。医療現場の主役は、患者。医療行為は、患者を癒やす行為であり、患者のために病院は存在しています。患者が安心して治療を受けられるようにするためには、機器の動作や外観から感じる“機械らしさ”をできる限り抑えることが求められます。
この要素が大切であることがわかる、とてもわかりやすい例があります。何かというと、「歯科治療」です。歯の治療は、患者にとって大きな不安・恐怖というイメージがあると思います。その理由が「大きな音」「歯に伝わる振動」「工事現場のような印象の器具」など、まさに先ほど挙げた3要素の“逆”がそろってしまっている点にあります。(治療方法の性質上、やむを得ない部分もありますが)
こういったことを背景として、病院で使われる機器は、「丸みのある外観」「静か」「低振動」を実現しているものがほとんどであり、モータのような「機械」のイメージを感じることはないようになっています。
診察室や病室にいる患者は、多かれ少なかれ不安を抱えているものです。そんな状況では、設置されている機器からわずかでも駆動音が聞こえてくると、不快感や恐怖感を感じてしまうことがあります。そのため、モータには極めて静かな運転音と、滑らかな回転挙動が求められます。振動の原因となるトルクリップルや機械的バランスを抑えるため、磁極配置の最適化やスキュー構造を採用したり、また、ギアや軸受部には静音グリスを使用したりして、構造的にも防振性を高める工夫がなされています。
ブラシレスDCモータが使われる医療機器
さて、ここまでの解説を踏まえると、医療機器で使われるモータは、長寿命・メンテナンスフリー・低騒音・低振動・小型化といったことが得意であるブラシレスDCモータが優位であることが多く、実際多くの医療機器に搭載されています。具体的にどのような機器に使われているか紹介します。
呼吸・循環関連機器

人工呼吸器
人工呼吸器は、患者の呼吸を補助・代替する装置であり、内部では送風用のブロワファンをモータが駆動しています。
ネブライザ(吸入器)
薬剤を霧状にして気道に届ける装置です。微粒化ユニットの駆動に小型モータが使われています。
人工心肺装置
心臓手術時に血液を体外で循環させる装置です。血液ポンプの駆動源として、モータが使われます。
輸液・注入・透析機器

シリンジポンプ
シリンジ(注射器)をセットし、一定速度で押し込むことで薬液を体内に投与するための装置です。注入速度を細かく制御するためにモータが使われています。
透析装置
血液と透析液を循環させるポンプにモータが採用されています。血流量の変化を常に一定に保つため、トルクリップルの少ないモータ設計が必須です。
診断・検査・画像装置

CTスキャナ
X線管を回転させるガントリ機構に高出力型モータが用いられます。高速で連続回転しながらも、ブレや振動を最小限に抑える制御が求められます。
血液分析装置
サンプル撹拌や吸引ポンプの駆動など、複数の軸でモータが動いています。短時間で数百~の繰り返し動作を行うため、モータには耐久性と制御応答性の両立が求められます。
リハビリ関連
リハビリロボット
患者の動作を補助・再現するロボットでは、小型・高トルク・応答性の高いモータが各関節部に搭載されています。人の関節のように滑らかな動きを再現するため、トルクリップルが少ないことが重要です。センサとの連動で負荷を検知しながらトルクをリアルタイムに制御するため、高精度なドライバ制御を持ち合わせた技術力のあるシステム設計が欠かせません。
移動・介助関連
電動車いす
段差越えや坂道走行でも安定した出力が出せるよう、トルク重視のモータが採用されます。回生ブレーキ機能を組み合わせることで、安全性と省エネ性の両立を実現したモータが使われます。
リフト・ストレッチャー
患者を持ち上げたり移動させたりする機構に、静音性と出力密度を兼ね備えたモータが使われています。病室や手術室内で使用されるものは、音や振動の少なさは極めて重要な要素となっています。
医療機器モータをご用命の方はユニテックへご相談ください
医療機器用モータは、一般産業用モータに比べて求められる要求レベルが非常に高いです。弊社の長い歴史・経験をもとに最適なモータを提案いたしますので、ぜひお問い合わせください。